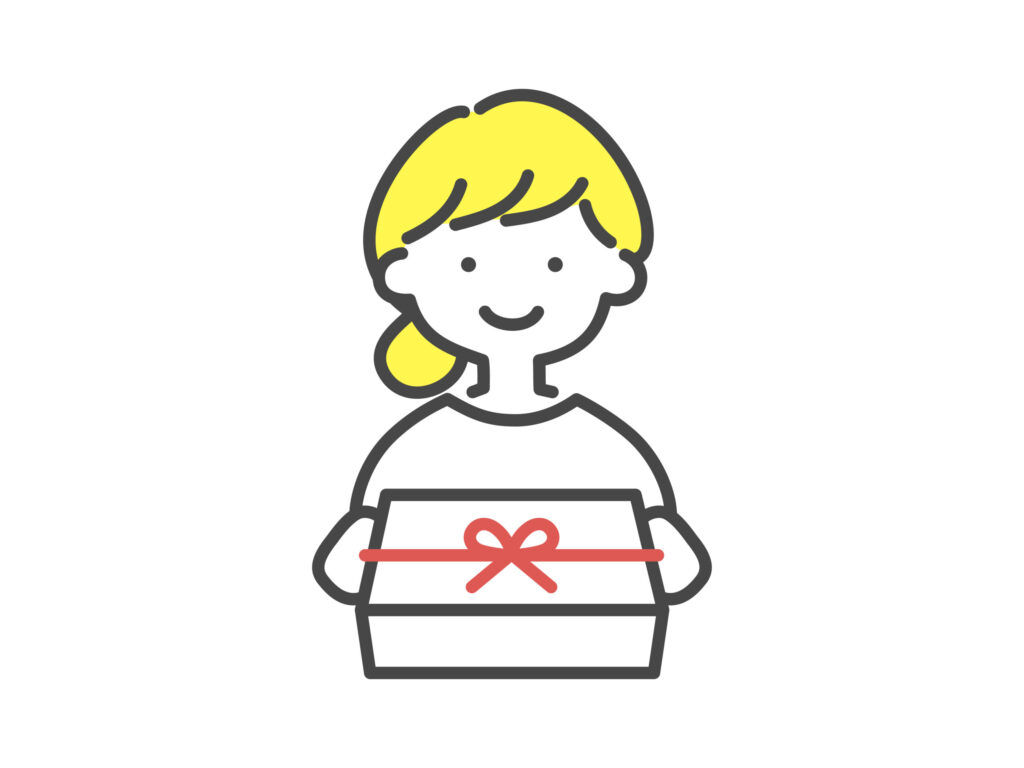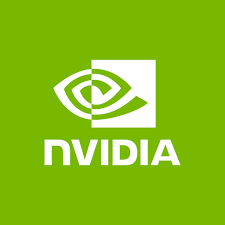消えゆく夏の風物詩「お中元」─1000年の伝統が揺らいでいる ('25/7/14号)
7月になると、日本では「お中元」の季節が訪れます。お中元とは、日頃お世話になっている人に感謝の気持ちを込めて贈り物をする風習で、その起源は平安時代とも言われ、実に1000年以上の歴史があります。本来は、仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」や中国の道教の影響を受けて生まれたとされ、夏の贈答文化として現代まで続いてきました。
しかし、その伝統も今、大きな転機を迎えています。特に若い世代では、お中元を「堅苦しい」「時代遅れ」と感じる人が増えており、文化としての存在意義が問い直されているのです。

若者世代に広がる「必要ない」意識
博報堂生活総研の2024年調査によると、「お中元を毎年欠かさず贈っている」と回答した人はわずか17.7%。特に20代では2.9%にとどまる一方、60代では37.4%と世代間で差が顕著でした 。さらに別の項目では、「お中元・お歳暮にお金をかけている」は全体で7.8%、20代では2.6%と低調でした 。これらの結果から、若い世代では形式的な贈答への関心が大きく薄れていることがわかります。
縮小する市場と時代の変化
矢野経済研究所の調査によれば、お中元を含むフォーマルギフト市場は2019年に約7,210億円あったのが、2023年には約6,620億円に減少しています。一方、ギフト市場全体(お中元・お歳暮を含む)は2023年に約10兆8,930億円、2024年には約11兆1,880億円と微増傾向にあります 。
更に、近年急成長中の“ソーシャルギフト”(例:LINEギフトなど)は、2025年には約2.7兆円規模へ拡大し、従来ギフト市場の約1.5倍に達すると予測されています。
価値観の変化
従来の「お中元」は確かに伝統ある文化ですが、若者世代の関心は年々低下。形式的な習慣よりも、LINEギフト等のデジタルギフトが主流となりつつあります。市場全体は広がる一方で、価値観の変化によって“かつてのカタチ”は静かに消えつつあります。