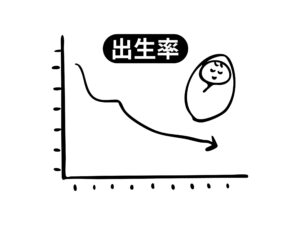認知症は「7番目の死因」─高齢社会日本に迫る静かな危機 ('25/6/16号)
高齢者にとって大きな不安要素のひとつが「認知症」です。世界保健機関(WHO)の2023年の報告によると、認知症は世界全体で7番目に多い死因とされており、その数は今後も増加が見込まれています。現在、世界では5500万人以上、日本国内では約600万人が認知症を抱えているとされています。
さらに、2025年には日本の高齢者の5人に1人が認知症を発症するとの推計もあり、個人だけでなく家族、医療・介護現場、さらには社会保障制度全体にとっても深刻な問題となっています。

生まれた世代で差が出る?脳の“時代効果”とは
ところが、海外の複数の研究機関が希望につながる興味深いデータを発表しています。それは、「生まれた年代が新しい世代ほど、同じ年齢でも認知症の発症率が低い」というものです。たとえば、80歳時点での認知症有病率を比較すると──
- 1890〜1913年生まれ:約25.1%
- 1939〜1943年生まれ:約15.5%
というように、わずか数十年の世代差で約4割もの減少が見られたのです。これは「コホート効果(世代効果)」とも呼ばれ、幼少期の栄養状態の改善、教育機会の増加、生活習慣の変化などが影響していると考えられています。
また、現代は情報量が圧倒的に多く、デジタル機器や社会参加の機会も豊富なため、脳への刺激が多い環境が整っている点も重要な要素です。
認知症を遠ざけるために、今できること
認知症を完全に防ぐ方法はまだ確立されていませんが、多くの研究から「生活習慣を整えることで発症リスクを下げられる」ことが分かってきました。以下は、予防に効果があるとされている代表的な取り組みです:
① 脳の刺激を日常に取り入れる
読書・パズル・会話・ゲーム・語学・楽器など、「考える・覚える・判断する」行動を継続することが有効です。
② 適度な運動を続ける
ウォーキングや体操、ヨガなどの軽い運動は、血流改善やストレス軽減、うつ予防にもつながります。
③ 社会とのつながりを保つ
家族や友人、地域活動への参加は孤立を防ぎ、精神的な健康を保ちます。孤独は認知症リスクを2倍以上に高めるとする報告もあります。
④ 食生活の見直し
地中海食やDASH食(野菜・果物・ナッツ・魚中心の食事)が脳に良いとされ、MIND食と呼ばれる認知症予防に特化した食事法も注目されています。
まとめ:脳を「使う」「守る」ことが未来を変える
認知症は避けて通れない現実かもしれませんが、生活の中でできる予防策はたくさんあります。
そして何より重要なのは、「歳をとっても脳は変わる」「使えば鍛えられる」という事実です。
今の社会は、過去の世代に比べて脳に優しい環境が整いつつあります。
だからこそ、日常生活に小さな“脳への投資”を加えることが、未来の自分自身を守る最大の備えになるのではないでしょうか。