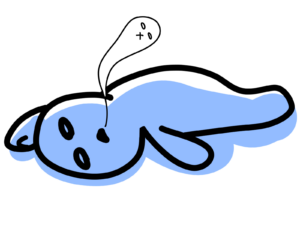海外では通じない!? 意外と知らない“日本だけ”の言葉 ('25/5/12号)
グローバル社会と呼ばれる現代。英語が公用語の企業も増え、海外の情報が瞬時に手に入る今、日本人の私たちも「世界基準(グローバルスタンダード)」を意識する機会が増えてきました。
そんな中で気をつけたいのが、“和製英語”です。日本では英語のように使われていても、実際には海外でまったく通じない、あるいは意味がまったく異なる表現が意外と多いのです。

ビジネスで注意!日本だけの略語や表現
たとえば「アルバイト」。これはドイツ語由来の「Arbeit(仕事)」から来ております。日本では「アルバイト」(パートとも呼ばれる)として一般的に使われていますが、英語圏では「part-time job」や「side job」が正しい表現です。
また「ノートパソコン(ノートPC)」も要注意。英語では通常「laptop」または「notebook computer」と呼ばれ、「note PC」と言ってもまず伝わりません。
金融やIT業界でも同様です。日本ではおなじみの「GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)」という略語。これはかつて日本で流行語大賞にもノミネートされましたが、実は海外ではこの言い方は一般的ではなく、米国などでは「Big Tech」や「Tech Giants」といった表現の方が広く使われています。
同様に、2008年の金融危機を指す「リーマンショック」も和製英語の一例。これはリーマン・ブラザーズの破綻を象徴的に捉えた日本独自の呼び方で、国際的には「GFC(Global Financial Crisis)」や「2008 Financial Crisis」などと呼ばれています。
グローバル社会では「伝わる言葉選び」が鍵
こうした和製英語や日本独自の呼び方は、国内では通用しますが、海外とのビジネスや交流が増えるにつれて「通じない・誤解される」リスクも伴います。
だからこそ、英語を使うときはその言葉が本当に国際的にも正しい表現なのか、あるいは現地で通じるかをチェックすることがとても大切です。
もちろん、和製英語自体を否定するわけではありません。日本語の一部として文化に根付いていますし、私たちにとっては非常に便利な表現でもあります。ただ、グローバルな場面では、より“伝わる言葉選び”を意識したいものです。
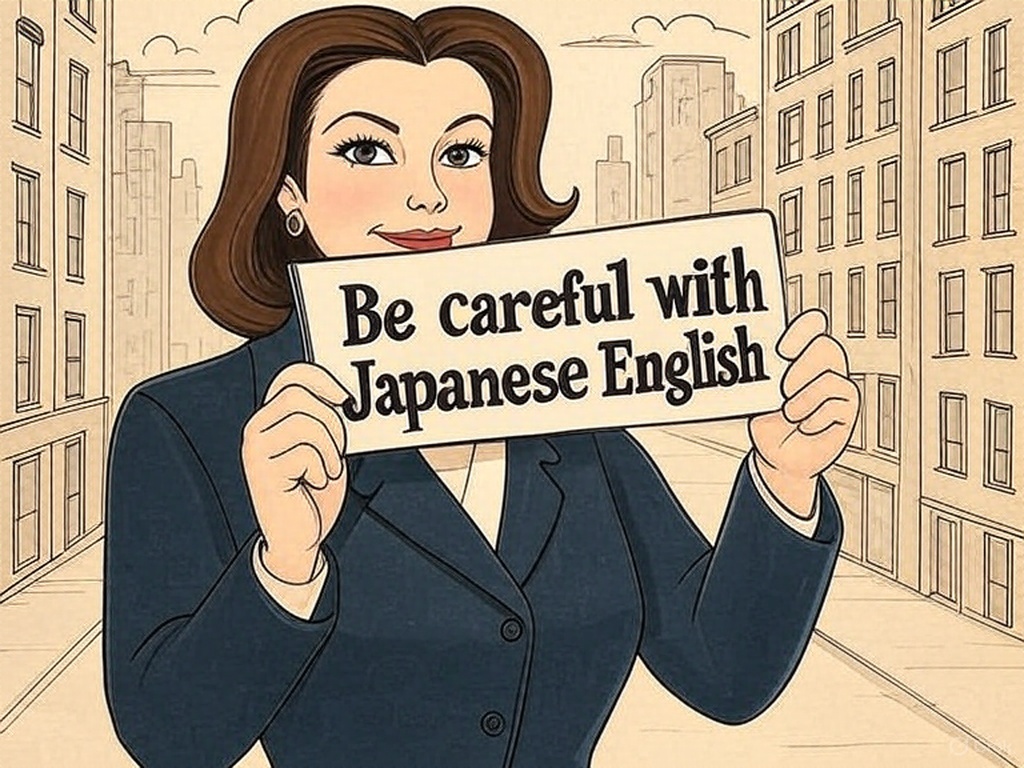
和製英語に注意