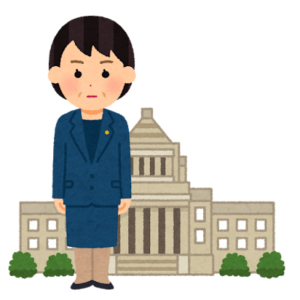次に崩れる「1000円の壁」—インフレが変える日常価格 ('25/10/13号)
2025年度の最低賃金が全国平均で時給1,121円となり、過去最高を更新しました。これは2015年(798円)と比べて約40%もの上昇です。特に東京や神奈川など都市部では1,150円を超える地域も多く、全国的に“時給1,000円超え”が当たり前の時代に入りました。しかしこの上昇は賃金が上がったというより、物価の高騰に追いつくための調整という面が強いのが実情です。
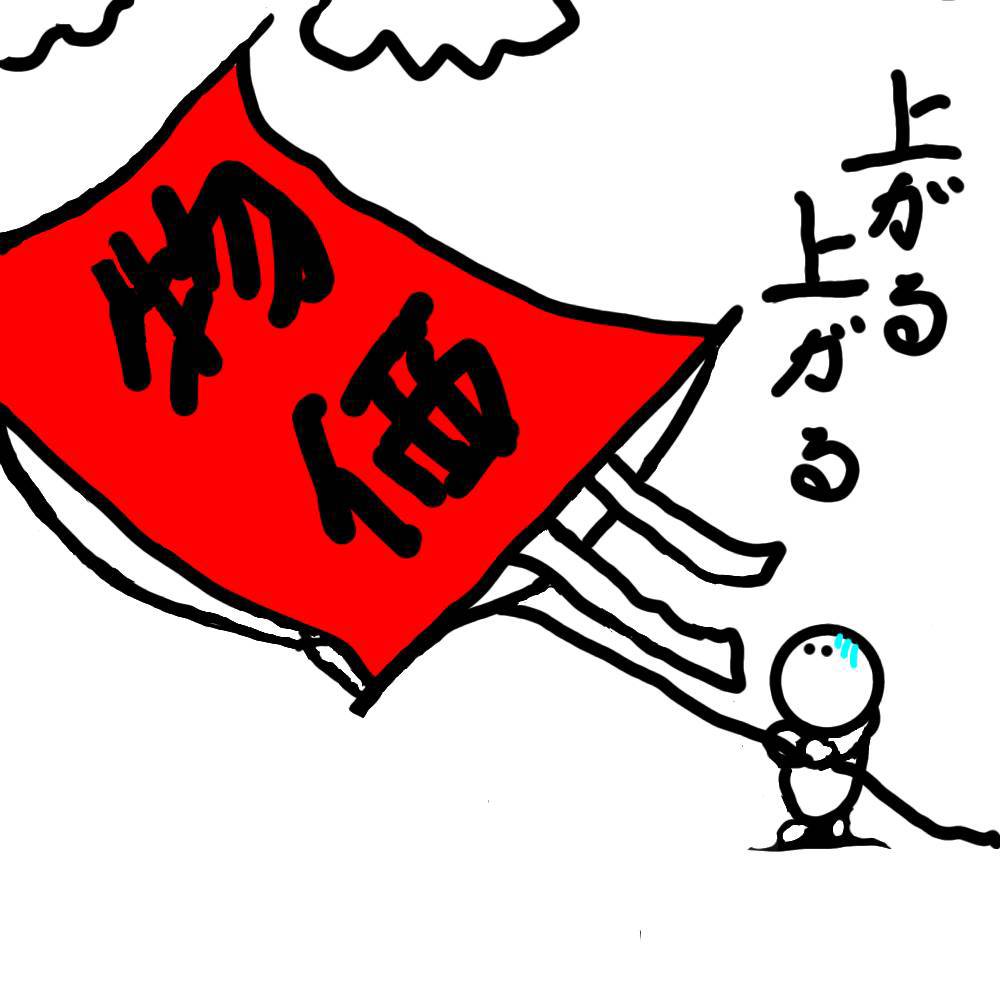
物価上昇への「慣れ」
実際、総務省の消費者物価指数によると、2020年代初頭以降の物価上昇率は年平均3%前後。食品や外食費は特に影響を受けており、かつて“ちょっと贅沢”と感じた1,000円ランチは、いまや平均1,250円前後が相場とされています(ホットペッパーグルメ外食総研2025調べ)。コンビニ弁当やカフェランチでも、同様の価格帯が主流になりつつあります。消費者の間では「高い」と感じながらも、物価上昇に慣れてしまい、抵抗感が薄れているのが現状です。
お金の価値の低下
そして今、“次の1000円の壁”として注目されているのが文庫本の価格です。出版社協会の統計によれば、2025年8月時点で新刊文庫の平均価格は818円に達し、10年前(約600円台)から約35%の上昇。印刷コストや物流費、紙の価格上昇が要因です。以前は「ワンコインで買える手軽な娯楽」として親しまれてきた文庫本も、いずれ1,000円に近づくのは時間の問題といわれています。日常の小さな買い物にもインフレの影響が及ぶなか、「お金の価値が静かに目減りしている」ことを、私たちは身近な価格変化から実感しつつあります。