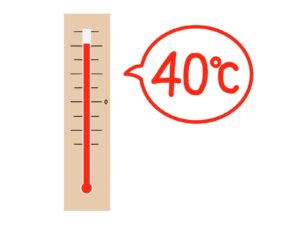夏の朝を彩った懐かしい風景 ('25/8/18号)
「新しい朝が来た、希望の朝だ~」
という歌と共に始まるラジオ体操。かつての夏休みには、早朝の公園や広場に子どもたちが集まり、元気いっぱいに体を動かす姿が各地で見られました。
スタンプカードを首から下げて通う習慣や、体操の後に友達と遊ぶ時間なども、夏の思い出として強く残っている人も多いでしょう。
まさに“日本の夏の風物詩”として定着していた行事でした。

減少の背景にある社会の変化
しかし近年、このラジオ体操の光景は少しずつ姿を消しつつあります。
少子化によって子どもの数が減ったことや、地域の子ども会や自治会の活動縮小が大きな要因です。
さらに、共働き家庭の増加により、保護者が早朝から付き添うのが難しくなっている現実もあります。
加えて、近年の猛暑は深刻で、熱中症のリスクから屋外での活動を控えるケースが増えていることも大きな理由です。
こうした社会的・環境的な変化が、昔ながらの風景を少しずつ奪っているのです。
今こそ見直したいラジオ体操の価値
ラジオ体操が日本に誕生したのは1928年(昭和3年)、昭和天皇の即位を記念して逓信省(現在の日本郵政グループ)が考案したのが始まりです。
当時は「国民の健康増進」を目的に、アメリカの生命保険会社で行われていた体操を参考にして作られました。
その後、第二次世界大戦中には一時中止されましたが、戦後1946年に復活。全国に広まり、学校や職場、地域行事など生活に根付いていきました。
現在放送されている第1・第2体操は、老若男女問わず誰でも取り組めるよう設計されており、3分という短時間で全身運動ができる点が特徴です。
その効果は科学的にも認められており、姿勢改善や血流促進、筋力アップなど、健康寿命の延伸に役立つと専門家からも注目されています。
最近では企業の朝礼や高齢者施設のプログラムにも取り入れられ、新しい形で再評価されています。
夏休みの定番が消えつつある今だからこそ、大人も子どもも「ちょっと体を動かしたい」と思ったときに、気軽に取り入れてみる価値があるのではないでしょうか。